レンタルスペース運営で成功するかどうかは、「どのエリアで開業するか」に大きく左右されます。
立地が良ければ自然と予約が入りやすく、ポータルサイトやSNSからの集客もスムーズに進みます。
一方で、需要が低いエリアではどれだけ内装をおしゃれに整えても予約が埋まらず、広告費をかけても赤字になるケースも少なくありません。
せっかくレンタルスペースを始めるなら、需要が見込めるエリアを選んで着実に利益を出したいですよね。
そこで本記事では、開業前に「その場所に本当に需要があるのか」を見極めるための具体的なポイントと調査方法を、初心者の方でもわかりやすく解説していきます。
エリア選びがレンタルスペース運営の成功を左右する理由
レンタルスペースは「場所を貸す」というビジネスモデルのため、立地が集客力をほぼ決定づけるといっても過言ではありません。
同じ内装・同じ広さのスタジオでも、駅徒歩3分の物件と徒歩15分の物件では、予約の入り方がまったく異なります。
立地が悪いと、利用者が「行きにくい」と感じるため、そもそも予約の候補に入らないことが多くなります。
その結果、ポータルサイト検索でも同じエリア内の駅近物件に比べて選ばれにくく、利用者の目に触れる機会が減ってしまいます。
さらに予約を増やそうと広告を出しても、「行きやすさ」で不利な物件は予約率が低くなりがちです。
結果として、広告費をかけても予約につながりにくく、集客コストが割高になるという悪循環に陥ります。
一方で、アクセスの良い物件は利用者が候補に入れやすく、比較検討時にも選ばれやすいため、ポータルサイトでも広告でも予約が自然と集まりやすくなります。
また、家賃が安い物件でも、稼働率が低ければ固定費を回収できず赤字に陥る可能性があります。
そのため、エリア選びは単に「家賃が安いから」という理由ではなく、需要と費用のバランスを総合的に判断することが重要です。
需要が高いエリアに共通する3つの特徴
レンタルスペースは「場所を貸す」というビジネスモデルなので、そのエリア自体に人が集まる理由があるかどうかが成功を大きく左右します。
ここでは、需要が高いエリアに共通する3つの特徴を解説します。この特徴を理解しておくことで、これから紹介する調査方法が「なぜ必要なのか」が明確になります。
人が集まりやすい駅近エリア
まずは、そもそも人がそのエリアに来ているかが大前提です。
駅の乗降客数が多い場所ほど、人通りが増え、レンタルスペースを利用する潜在的な顧客も自然と増えます。
駅から徒歩5分以内の物件は「アクセスの良さ」が強い武器になり、会議、レッスン、撮影など幅広い用途で利用されやすくなります。
逆に徒歩10分以上かかる立地では、移動の面倒さから予約候補にすら入らないケースが多くなります。
需要は「人が集まる駅」が起点になる。
まずはそのエリアにどれくらいの人が流入しているかが鍵です。
2. 特定の用途で人が集まる施設や環境がある
同じレンタルスペースでも、利用される目的は周辺環境によって変わります。
そのエリアに「どんな目的で人が集まっているのか」を把握することが重要です。
- オフィス街 → 会議やセミナー、研修などビジネス利用が中心
- 住宅街 → ママ会、習い事、子ども向け教室など地域住民が中心
- 観光地・繁華街 → 推し活、撮影、パーティーなど非日常的な利用が中心
ターゲットとスペースの用途がマッチしていれば、自然と予約は増えます。
逆に、需要と提供する用途がズレていると、どれだけ内装を整えても予約は入りません。
需要は「その場所に集まる人の目的」とセットで考える。
誰が、何のためにその町を訪れているのかを意識しましょう。
競合が存在している=市場が成立している
競合スペースは「敵」でもありますが、同時にそのエリアに市場が存在する証拠でもあります。
まったく競合がない場所は、一見チャンスに見えますが、そもそも需要がないために誰も参入していないケースも多いです。逆に、競合が多すぎる場所は価格競争が起きやすく、利益率が下がるリスクがあります。
この状態は、需要が確実にあるうえに、まだ参入の余地も残されているというサインになります。
競合は「市場が動いているかどうか」のバロメーター。
数と稼働状況のバランスをチェックしましょう。
需要を確認するための調査方法
需要が高いエリアの特徴がわかったら、次は実際にその場所に需要があるかどうかを確認する作業です。
立地条件が良さそうに見えても、実際には人通りが少なかったり、ネット上でまったく検索されていなかったりするケースは珍しくありません。
感覚や雰囲気だけで判断してしまうと、開業後に「思ったより予約が入らない」という失敗につながります。
そこで重要なのが、数字やデータをもとに客観的に需要を判断することです。
ここでは、初心者でも簡単にできる調査方法を3つ紹介します。これらを組み合わせれば、開業前に需要をかなり正確に見極められるようになります。
最寄り駅の乗降客数を調べる
レンタルスペースの需要を考えるうえで、最もシンプルで分かりやすい指標が最寄り駅の乗降客数です。
駅を利用する人が多いほど、その周辺に人が集まる機会が増え、スペースを利用してくれる潜在的なお客さんも多くなります。
たとえば、1日の乗降客数が10万人を超える大きな駅は、それだけで常に人が行き来している状態です。
こうした駅は会議やレッスン、撮影など様々な用途で使われやすく、レンタルスペースとしても外れにくい立地といえます。
逆に、1万人を下回る駅だと、そもそもそのエリアに来る人が少ないため、集客にかなり苦労する可能性が高くなります。
乗降客数は「駅名+乗降客数」で検索すれば簡単に調べられます。
鉄道会社の公式サイトやWikipediaなどで、1日平均の数字が掲載されているので、候補地を比較するときに必ず確認しておきましょう。
これは難しい統計データを見る必要もなく、すぐに数字で判断できるため、初心者がまず最初に取り組むべき調査です。
また、同じ駅でも徒歩5分以内か、それ以上離れているかで集客力は大きく変わります。
同じ乗降客数でも、駅から遠い物件は予約されにくいため、「乗降客数が多い駅 × 徒歩5分以内」という条件を基本ラインとして考えるとかなり失敗しにくくなります。
最寄り駅の利用者数は、レンタルスペースの需要を測るうえで最も重要な基礎データです。
まずはここをしっかり確認して、集客の土台となる「人の流れ」が十分にあるかを見極めましょう。
検索ボリュームでオンライン需要を調べる
レンタルスペースは、ほとんどの利用者がネット検索で探します。
そのため、実際にどれくらい検索されているのかを把握することは、需要を見極めるうえでとても重要です。
具体的には、Google広告のキーワードプランナーなどを使い、「地名+レンタルスペース」「地名+会議室」「地名+ダンススタジオ」などのキーワードを調べてみましょう。
検索ボリュームが多いほど、実際にその地域で探している人が多いということになります。
逆に検索数が極端に少なければ、そのエリアではまだ需要が少ない、もしくはこれから伸びる可能性があると判断できます。
この方法は利用者がどれくらい動いているかを数字で把握できるのが強みです。
検索ボリュームが低い地域はGoogle広告も出しにくくなるので、非常に重要なポイントと言えます。
ポータルサイトで競合と稼働状況を見る
駅の乗降客数や検索ボリュームで、そのエリアに人が集まる可能性が高いことが分かっても、実際にレンタルスペースが利用されているかどうかは別問題です。そこで役立つのが、ポータルサイトを使った競合調査です。
スペースマーケットやInstabaseなどのポータルサイトは、レンタルスペースを探す利用者が必ずチェックする場所です。
ここで同じエリアを検索してみると、競合スペースの数や、どれくらい予約が入っているかが一目で分かります。
まず注目したいのは、そのエリアに登録されているスペースの件数です。
件数がゼロに近ければ、「需要がない」「ターゲット層がいない」という可能性が高くなります。
逆に件数が多すぎる場合は、競合が激しく価格競争になりやすく、差別化が必須になります。
理想は「同ジャンルのスペースがいくつかあるけれど、まだ飽和していない状態」です。
さらに、候補となるスペースの予約カレンダーやレビュー数も確認してみましょう。
- 予約カレンダーがほぼ埋まっている → 実際に需要が動いている証拠
- レビューが多く最新のものが直近 → 安定して利用されているサイン
- 予約がスカスカでレビューも少ない → 需要が弱い可能性大
この調査によって、「理論上は需要がありそうだけど、実際は動いていない」というリスクを事前に回避できます。
また、競合の写真やプラン、価格設定も参考にすれば、自分のスペースをどの方向性で打ち出すかというヒントにもなります。
ポータルサイト調査は、生きたデータを手軽に得られる最強のリサーチ方法です。
必ず開業前にチェックしておきましょう。
需要があっても注意が必要なエリア
ここまででエリアの需要が大事とお伝えして来ましたが、需要が高いエリア=成功できるエリアとは限りません。
たとえ予約が順調に入りそうな場所でも、利益が出にくい構造的な問題や、運営上のトラブルを抱えやすいリスクが潜んでいるケースがあります。
ここを見落としてしまうと、開業してしばらくは予約で埋まっていても、気づけば赤字経営になったり、クレーム対応に追われて消耗してしまうことも。
「人が集まる場所」という表面的な条件だけで判断するのはとても危険です。
ここでは、開業前に必ず確認しておくべき3つの落とし穴を解説します。
家賃が高すぎて利益が出ない
需要が高いエリアほど、家賃も高くなる傾向があります。
一見すると集客が簡単そうに見えても、家賃が利益を圧迫して赤字になるケースは少なくありません。
例えば、月の家賃が30万円の物件を契約した場合、家賃だけで年間360万円の固定費が発生します。
1時間あたり2,000円で貸し出しても、月に150時間以上の稼働がなければ黒字化は難しくなります。
しかし、実際の稼働率は天候や季節、曜日によって変動するため、常にフル稼働させることはほぼ不可能です。
「このくらい予約が入るだろう」という感覚だけで決めてしまうと、想定以上に家賃が重荷となり、赤字が続くリスクがあります。
必ず家賃と想定稼働率を基にシミュレーションを行いましょう。
家賃負担が重いと、集客が順調でも利益がほとんど残らないという状況になりかねません。
初期段階では、家賃を抑えてリスクを軽減する戦略が安全です。

競合過多で価格競争に巻き込まれる
需要が高いエリアは、競合も多いのが当たり前です。
特に都心部や人気エリアでは、多くのレンタルスペースがひしめき合っており、自然と価格競争に陥りがちです。
ポータルサイトで検索した際に同ジャンルのスペースが大量に出てくる場合は要注意です。
利用者はまず価格と立地で比較するため、少しでも安いスペースが選ばれる傾向にあります。
結果として、最初は2,500円で設定していた料金が、競合に合わせて2,000円、1,800円と下がっていき、
気づけば「頑張って稼働してもほとんど利益が残らない」という状態に陥ることもあります。
競合の多いエリアで成功するためには、価格以外の強みで差別化する必要があります。
たとえば、
- 特定用途に特化したコンセプト(例:推し活専用ルーム、キッズスペース特化など)
- 競合が提供していない設備や体験
- 顧客層を限定したマーケティング戦略
単に「安くする」だけではなく、長期的に利益を確保できる運営設計が不可欠です。
治安や環境面でトラブルが発生する
需要が高いエリアは人通りが多い反面、トラブルの発生リスクも高まります。
特に住宅街や繁華街に隣接する物件では、環境や治安が原因で運営が難しくなることがあります。
騒音クレーム
- ダンスやヨガ、楽器演奏などは音や振動が伝わりやすく、近隣住民からの苦情につながりやすい
- 特に古い建物や壁が薄い構造では注意が必要
駐車場・駐輪問題
- 専用の駐車場がない場合、利用者が近隣住民のスペースを無断で使用するケースも
- たった1回の迷惑駐車が大きなトラブルに発展することも
夜間の治安問題
- 繁華街では深夜の酔客トラブルやゴミ問題が発生しやすい
- 夜間運営はセキュリティ対策が必須
こうしたトラブルは、事前に現地を確認することでかなり防げます。
ネットの情報や地図だけでは分からない要素なので、昼と夜の両方の時間帯に現地を訪れ、周囲の雰囲気をチェックしておくとベストです。
まとめ
レンタルスペース運営では、どんな内装や設備を整えるよりも「どのエリアで始めるか」が何よりも重要となります。
需要が高いエリアを選べば、自然と予約が入りやすく、集客が安定します。
一方で、需要が低いエリアでは稼働率が上がりにくく、赤字経営に陥るリスクが高くなります。
本記事で解説したように、エリア選びは数字と現地確認の両面から判断することが鉄則です。
- まずは 駅の乗降客数 や 検索ボリューム で、客観的に「人が集まるエリア」かどうかを確認する
- 次に ポータルサイト で競合の数や稼働状況を調べ、実際の需要を見極める
- そして現地を訪れ、周辺環境や治安、駐車場問題などのリスクを直接チェックする
この3ステップを踏むことで、「なんとなく需要がありそう」という感覚だけではなく、根拠を持って判断できるエリア選びが可能になります。
また、需要が高くても家賃や競合状況によっては利益が出にくいケースもあるため、採算シミュレーションを忘れずに行うことが重要です。
最後に、自分が提供したい用途やターゲットと、そのエリアに集まる人々のニーズが合致しているかを改めて確認しましょう。
「数字」「現地」「ターゲット」の3つが揃えば、安定して予約が入り続けるレンタルスペース運営が実現できます。
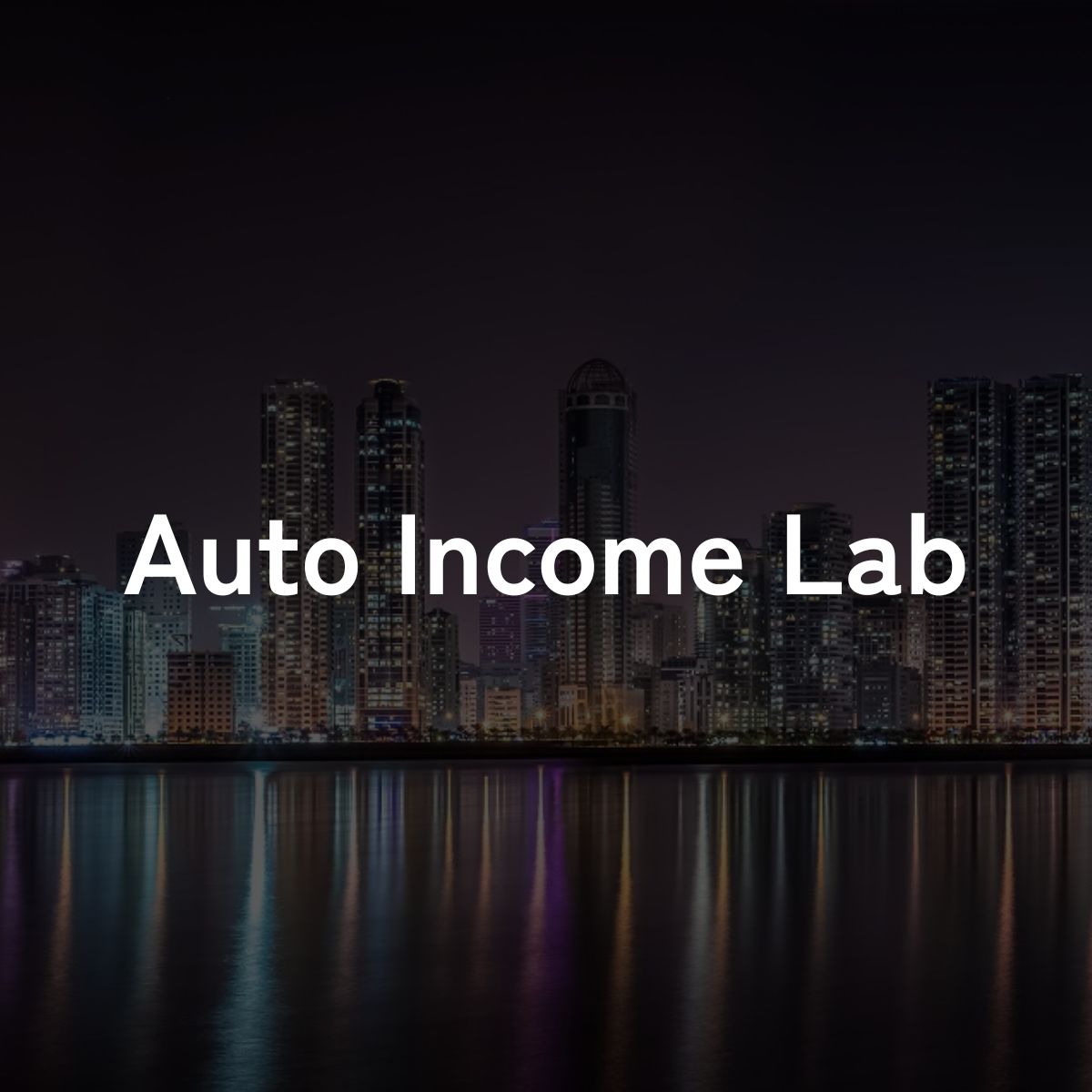

コメント