近年、副業や不動産活用の選択肢として注目を集めているレンタルスペース運営。
不動産投資よりも初期費用が少なく始められるため、「手軽に始められる投資」「ほったらかしでも収益が出る」といったイメージを持つ方も少なくありません。
しかし、実際には投資感覚で安易に始めると失敗するケースが非常に多いのが現実です。
レンタルスペースは、株式や不動産投資のようにお金を投じて放置しておくだけではなく、日々の運営・集客・顧客対応が欠かせない「経営が必要なビジネス」だからです。
とはいえ、必ずしも自分が現場で動き続ける必要はありません。
仕組み化を進めることで、限りなく不労所得に近い形で運営することも可能です。
そして、成功と失敗を分ける大きな指標のひとつが「利益率」です。
利益率をきちんと把握せずにスタートすると、「売上はあるのに赤字」「想定より手元に残らない」という事態に陥りがちです。
本記事では、利益率を軸に投資感覚で始めることのリスクを解説し、できるだけ不労所得に近づけるためのレンタルスペース経営のポイントをご紹介します。
レンタルスペース投資が注目される理由
近年、レンタルスペースは副業や不動産活用の新たな手段として急速に広がっています。
背景には、働き方改革や副業解禁、そして個人事業主やフリーランスの増加といった社会的な流れがあります。また、ダンスやヨガ、会議や撮影など幅広い用途で需要が増えていることも大きな理由です。
レンタルスペースが注目を集めているもう一つの理由は、初期費用の少なさです。
一般的な不動産投資では物件購入が必要ですが、レンタルスペースなら賃貸物件からでも始められます。
空き家や自宅の空き部屋を活用することもできるため、数十万円程度からスタートできるケースもあります。
さらに、一度スペースを整えてしまえば「予約が入るたびに自動的に収益が発生する」という仕組みに見えるため、「ほったらかしでも稼げる投資」と捉えられることも少なくありません。
こうした理由から、多くの人がレンタルスペースを投資対象として魅力的に感じています。しかし、実際にはここに大きな誤解が潜んでおり、この誤解が失敗を招く原因となるのです。
次章では、その誤解を解き明かし、レンタルスペース運営の実態を詳しく見ていきましょう。
レンスぺは投資ではなく“経営”に近い理由
レンタルスペースは一見すると「ほったらかしで収益が発生する投資」のように見えます。しかし、前述した通り、実際にはお金を投じて放置しておくだけではなかなか成立せず、日々の運営が欠かせないビジネスです。
ここでは、投資ではなく経営として捉えるべき理由を見ていきましょう。
投資と経営の違いを整理する
まずは「投資」と「経営」の違いを簡単に整理してみましょう。
| 投資 | 経営(レンタルスペース) | |
|---|---|---|
| 目的 | お金を運用して増やす | 利益を生み出す仕組みを作る |
| 手間 | 基本的に少ない | 日々の運営・改善が必要 |
| 主な行動 | 資金を投じる | 集客、顧客対応、運営改善 |
| 収益の性質 | 受動的 | 能動的(自分次第で伸ばせる) |
株式や投資信託のように、資金を投じたあとは基本的に放置しておけるのが投資です。
一方、レンタルスペースは集客・運営などの「実働」が不可欠なため、経営としての視点が求められます。
日々の運営が収益を左右する
投資では基本的にはお金を投じた後は何もしませんが、レンタルスペース運営では、次のような業務が日常的に発生します。
- 予約管理(ダブルブッキング防止など)
- 清掃や設備チェック
- クレーム対応や問い合わせ対応
- 集客施策(広告運用、SEO対策、SNS運用など)
- 売上・経費管理
これらをおろそかにすると、
- 予約がなかなか増えない
- 利用者の満足度が下がりリピーターが減る
- ネガティブな口コミが広がり新規集客が止まる
- 経費が増え利益率が下がる
といった問題が起き、赤字になってしまう可能性が大きくなります。
仕組み化で“ほったらかし”に近づけることはできる
「経営」とはいえ、必ずしも自分が現場で動き続ける必要はありません。
清掃を外注したり、予約管理をシステム化したりすることで、限りなく不労所得に近い形で運営することも可能です。
ただし、初期段階は自分で現場を把握しながら運営し、課題を明確にしたうえで仕組み化を進めるのが理想です。
完全に“放置できる”状態にするには、こうした段階的な工夫が欠かせません。
利益率で見るレンタルスペース運営のリアル
レンタルスペースが投資ではなく経営に近いと言える理由のひとつが、利益率が運営次第で大きく変わるという点です。
ここでは、利益率の基本的な考え方と、運営の現実を数字から見ていきましょう。
利益率とは?基本の考え方
利益率とは、売上に対してどれだけ利益が残っているかを示す指標です。
利益率は数字で「儲かっているか」を判断するための物差しで、高ければ高いほど効率的に利益を生み出していることを意味します。
利益率は次の計算式で求めます。
利益率 = (売上 − 経費) ÷ 売上 × 100
たとえば月売上が30万円で、経費が20万円かかった場合、
(30万円 − 20万円) ÷ 30万円 × 100 = 利益率33%
となります。
つまり、売上のうち33%が手元に残り、残りは家賃や光熱費、手数料などに消えたということです。
利益率を圧迫する主なコスト
レンタルスペース運営で利益率を下げる大きな原因は「経費」です。
代表的なものは以下の通りです。
- 家賃:固定費として最も大きな負担
- 光熱費:エアコンや照明など利用時間が長いほど増加
- ポータルサイト手数料:売上の30〜35%が相場
- 運営代行コスト:売上の10~15%が相場
- 清掃コスト:外注する場合は清掃スタッフの人件費も
- 広告費・集客コスト:Google広告やSNS運用など
特にポータルサイトの手数料は、売上が増えるほど負担も大きくなります。そのため、自社の予約システムから直接予約してもらえるよう自分でも集客を行い、手数料を減らすことが利益率改善の鍵となります。
一般的なレンタルスペースの利益率目安はある?
レンタルスペースには「これが平均的な利益率」という基準は実は存在しません。
何故なら会議室・撮影スペース・大型スタジオなど、運営形態がバラバラだからです。
重要なのは、自分のスペースごとに利益率・損益分岐点・稼働率を計算して把握することです。
その上で「毎月このラインを割らなければ継続できる」という自分だけの黒字ラインを決めましょう。
たとえば、同じ月売上60万円でも家賃や手数料の構造次第で、利益率が20%にも60%にもなります。
他社の数字ではなく、自分の数字をベースに判断することが成功への近道です。

初期費用回収の観点で考える安全ライン
レンタルスペース運営を始めるときに見落とされがちなのが、「初期費用を何カ月で回収できるか」という視点です。
いくら毎月黒字が出ていても、初期費用がいつまでも回収できないような薄利のままでは、実質的には手元のキャッシュが減り損をしている状態と同じです。
投資として考えるなら、初期費用の回収スピードを必ずチェックしましょう。
初期費用に含まれるもの
初期費用は、オープン時に一度だけかかる支出です。
これらは毎月の利益率には含めず、「投資したお金を何カ月で取り戻せるか」という視点で管理します。
| 初期費用の主な項目 | 具体例 |
|---|---|
| 内装工事費 | 床材変更、壁紙張り替え、照明設置など |
| 設備・備品購入 | 家具、ダンス用鏡、スピーカー、椅子、テーブルなど |
| その他 | Wi-Fi導入、防音工事など |
初期費用の回収期間の計算方法
初期費用がどれくらいの期間で回収できるかは、次の計算式で簡単に出せます。
回収期間 = 初期費用 ÷ 月間利益
初期費用180万円、月間利益10万円の場合、約1年半で初期費用を回収できます。
1年半後からは、純粋な黒字が積み上がるイメージです。
一般的な不動産投資では、もっと大きな金額を投資し、回収に20〜30年かかるのが普通です。
それと比較すると、レンタルスペースは初期費用が小さく、回収までの期間が短いため「投資効率が高い」ビジネスと言えます。
ただし、注意点としてレンタルスペースは「物件を貸すだけで自動的に稼げる」わけではありません。
集客や顧客対応、価格設定など運営スキルが求められる事業型投資です。
回収期間が短いことは魅力ですが、安定して月間利益を維持できる仕組みを整えて初めて、この計算が現実のものとなります。
回収期間から考える初期費用の上限
初期費用をどれくらいかけていいのか迷ったときは、回収期間を基準に逆算して考えるのが安全です。
基準としては「1年以内に回収できるかどうか」を目安にシミュレーションしましょう。
ただし、実際の運営では以下のような理由から、最初の数カ月は思うように利益が出ません。
- オープン直後は集客が安定せず、売上が低い
- 広告費をかけても即効果が出るわけではない
- 運営オペレーションの構築に時間がかかる
このため、計画上は1年で回収できる計算にしておき、実際には1年半で回収できれば合格ラインという感覚で考えるのが現実的です。
初期費用の上限 = 想定月間利益 × 12カ月
つまり、月間利益10万円を想定する場合は初期費用は120万円以内に、月間利益5万円を想定する場合は初期費用は60万円以内が目安となります。
このように、まずは「毎月どれくらい利益を出せそうか」を想定し、そこから逆算して初期費用の上限を決めることが重要です。
投資感覚だと失敗する2つの典型パターン
レンタルスペースは初期費用が少なく、短期間で投資回収できる魅力的なビジネスですが、「物件さえ用意すれば自動的に稼げる」という誤解を生みがちです。
実際には、運営スキルや集客力が必要な「事業型投資」であり、投資感覚で始めてしまうと以下のような失敗パターンにはまりやすくなります。
ここでは特に多い3つの典型パターンを紹介します。
ポータルサイト任せで集客
Instabaseやスペースマーケットなどのポータルサイトは、集客をすぐに始められる便利なサイトです。
しかし、前述したようにポータルサイトだけに頼る運営は非常に危険です。
なぜなら、ポータル経由の予約には30%前後の手数料が発生します。
例えば、月売上30万円の場合、9万円が手数料として消える計算です。
| 売上 | 手数料率 | 手数料額 |
|---|---|---|
| 30万円 | 30% | 9万円 |
| 50万円 | 30% | 15万円 |
| 100万円 | 30% | 30万円 |
一見売上が伸びているように見えても、利益はどんどん削られていくという状態になりがちです。
さらに、ポータルサイトはアルゴリズムやランキングの変動によって予約数が急激に上下します。
このため、ポータル依存度が高い運営は、ある日突然売上が激減するリスクを常に抱えることになります。
- 公式サイトを作り、直接予約を増やす施策を打つ
- リピーターを公式サイトに誘導して、手数料を削減
- ポータルはあくまで「集客の入口」と割り切る
運営代行会社に丸投げ
「手間をかけずに運営できる」という理由で運営代行会社にすべてを任せるケースも多く見られます。
確かに、清掃や顧客対応を外注することで、自分が現場に出る負担は減ります。
しかし、代行費用は売上の10〜20%程度が相場であり、利益がごっそり削られることになります。
また、ここで注意すべきなのは代行費用が「利益」ではなく「売上」から差し引かれるという点です。
たとえ赤字であっても、売上が発生した時点で代行会社への手数料は必ず発生します。
つまり、経営が苦しい月でも固定的に費用がかかるということです。
| 売上 | 代行費率15% | 代行費用 |
|---|---|---|
| 30万円 | 15% | 4.5万円 |
| 50万円 | 15% | 7.5万円 |
| 100万円 | 15% | 15万円 |
ポータル手数料30%と運営代行15%が同時にかかると、売上の半分近くが消える計算になります。
さらに、すべてを代行会社に任せてしまうと、運営感覚が身につかず、現場の問題にも気づけなくなるという大きなデメリットもあります。
運営代行を利用する場合は、最初から丸投げにせず、まずは自分で現場を経験し、本当に必要な部分だけを委託するスタイルから始めるのが安全です。
- 清掃など一部業務だけを外注し、自分で管理する範囲を残す
- 集客や価格設定など「数字に関わる部分」は必ず自分で握る
- 代行コストを含めた利益率を常にチェックする
まとめ:レンタルスペースは投資ではなく経営
レンタルスペースは初期費用が少なく始められ、短期間で回収できる魅力的なビジネスです。しかし、「ほったらかしで稼げる投資」ではなく、日々の運営が利益を左右する事業型投資です。
成功するためには、この3つを徹底することが重要です。
- 初期費用と回収期間をシミュレーションする
- 利益率を常に把握し、改善を続ける
- ポータルサイトや代行に依存しすぎない
「投資感覚」ではなく「経営視点」で数字を管理し、少しずつ仕組み化を進めていくことで、将来的には不労所得に近い形で安定した利益を生み出すレンタルスペース運営が実現できます。
この記事が参考になりましたら幸いです。
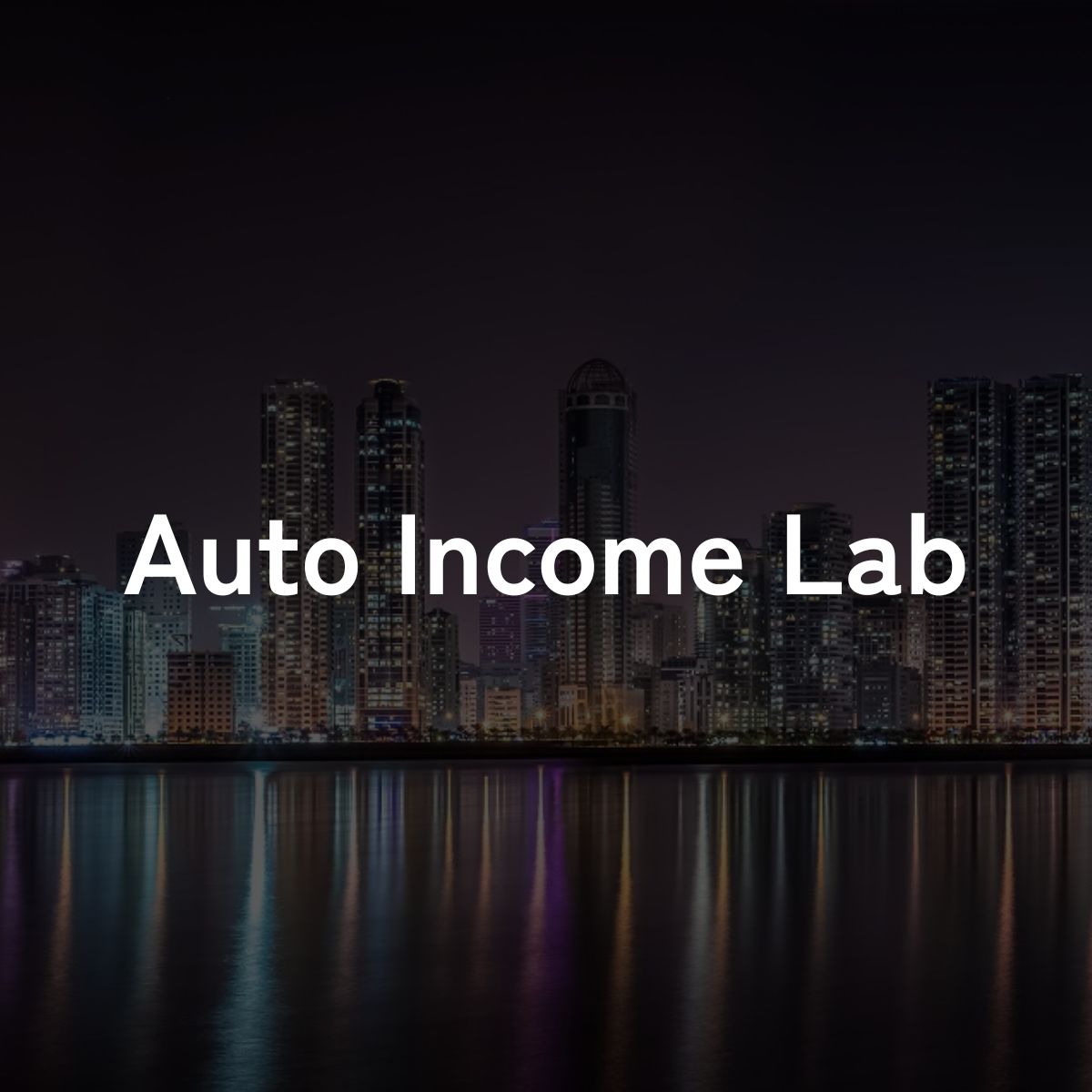



コメント